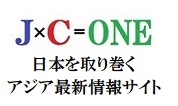今やコンビニの店員は外国籍が当たり前の時代になった。私の住む中野区ではネパール出身者を見ることが多い。
商品のレジ打ちはもちろん、店内のスナック類の販売から公共料金の支払い、宅配便の手配など、あらゆる窓口業務の対応が求められるコンビニ店員は、そもそもかなりハイレベルな存在である。それを高い日本語能力とともにこなす彼らは、正直、目を見張るものがある。
近所の「ミニストップ」には、発音もネイティブに近く、敬語も正確で、難しい表現もスラスラとこなすネパール人店員がいる。ある日、私は「どちらの日本語学校で学んだんですか」と聞いてしまった。そのネパール人女性は日本滞在歴7年。“日本語学校のメッカ”である大久保の学校が母校だったと言う。
わずか7年の日本滞在でここまで流暢になれるとは!自分の英語や中国語は7年目でどれだけのレベルに到達していたかを振り返ると、赤面せざるを得なかったし、留学生の能力をそこまで引き出す大久保の日本語学校に敬意を表せざるを得なかった。
ところがその後の私は、いろいろなネパール人に出会う中で、日本語能力の差は人によってさまざまだということに気が付くようになる。なかなか日本語の発音が定着しないネパール人もいれば、日本語ネイティブに近い発音ができるネパールもいる。
そして昨日、ある決定的なことがわかった。それは「ネワル族の言葉は日本語にとてもよく似ている」ということだった。初めて出会ったBさんは、ネパールの首都カトマンズ周辺に分布するそのネワル族だったのである。
Bさんは「ネワル語は発音のみならず、『目がクリクリしている』といったオノマトペ、『スカートを履く、帽子を被る』などの着脱動詞、長いものを1本2本と数えるときに使う数量詞などの点などで、日本語ととてもよく似ているんですよ」と話してくれた。
これらはほんの一例に過ぎないが、ネワル語と日本語は文法上の共通点がかなりあるという。逆に言えば、ネパール人にとって日本語の学びやすさは、民族によっても違うということになる。
現在、翻訳家として通訳士として活躍するBさんはこんな話もしていた。
「日本語を選んでラッキーでした。日本語は親しみがあるので、少しも苦ではないんです」
高度なスキルを持ちながら日本語を選んだことを後悔している外国人は実は少なくない。高度な人材になればなるほど、「自分の人生は日本語でよかったのか」という思いにさいなまれることがよくある。人はどの言語を第二外国語に選ぶかで一生を左右されるのだ。
朝ドラの「おしん」をネパールで見て日本語に興味を持ったBさん。そこから始まったBさんの「日本語人生」…。日本にはこれだけの外国人が住んでいるが、常に“あまりに高すぎる日本語の壁”に悩まされている。
「日本語を選んでよかった」というBさんの一言は、一筋の光明を見るかのようだった。