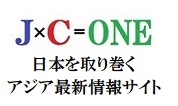7月31日、アジアビズ・オンラインの事務局長でもある杉本希世志が登壇し、外国人求職者の日本語能力について指摘しました。杉本事務局長は20年にわたり外国人材に取り組んだ経験があります。
「職場と教育現場の認識のズレがあります。『N2なのに話せないし、聞き取れない、発音もよくないね』という職場の声を聴く一方で、『N3だけど以外に話せるね』という声もあります。外国人材が話す日本語が通じる日本語なのかどうか、評価基準が一致していないのです」
日本では近年、外国人人材のニーズが高まっていますが、この「日本語の壁」がスムースな人材採用を妨げているようです。
すでにこれを意識する一部の人材サービス業界では、JLPT(日本語能力試験)の評価に依存しない採用を進めています。当会参加者からは「当社は会話測定ツールを使って、講師が30分、相手と話をしながら評価する方法をとっています」というコメントも上がりました。
一方でこの参加者の方が所属する会社では、90年代後半に中国で超一流の人材を採用して日本企業に派遣しましたが、結果として「“超エリート”すぎてうまく行かなかった、N1に近い人材を日本に連れてくるのは難しい」という教訓を得たそうです。
現在、この会社ではベトナム人材を手掛けているようですが、「いきなりN1人材ではなく、N3レベルの人材を教育しながら、というアプローチでやっている」と言います。
さて、日本語学校に通う学生は今、夏休みに入りました。中国、韓国、台湾など東アジア出身の留学生は、「安近短」という地の利から、故郷に帰って過ごす者も少なくありません。他方、東南アジアや南アジアの留学生は、「12月のJLPT(日本語能力試験)は何としても合格しなければならない」と、アルバイトと日本語学習に徹しています。
非漢字圏出身者にとって、日本語学習は血反吐(ちへど)を吐く思いです。文法中心の学習で、例外の多い文法ルールを覚えるだけでも相当な苦労が伴います。英語や中国の初級レベルは、ある程度の型を覚えれば話せるようになりますが、日本語はそうはいきません。
中級テキストでは「~とはいうものの」「~にしても」など高度な表現を習います。しかし、彼らの会話能力は「初級レベル」というのが現状です。にもかかわらず、日本語学校のカリキュラムは漢字学習中心、文法学習中心で進行。JLPTは会話の試験がないので、オーラルは結局後回しになってしまいます。
「日本でITエンジニアは不足していますが、外国人エンジニアはなかなか日本語が上達せず、“現場仕事”から抜け出せない人もいます。キャリアアップを妨げる『日本語の壁』が大きな課題となっています」(杉本事務局長)
採用現場と教育現場、そこへの橋渡しも必要なのかもしれません。(姫田小夏)