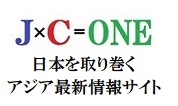「中野ブロードウェイ」で知られる東京・中野区。アニメグッズや高級時計の集積地としられ、今や国際的な観光地に成長した。区内の郵便局はEMSで海外に荷物を送る利用者でごった返していた。ところが、最近それがなくなった。
「爆買い」という言葉が流行した2010年代中盤以降、日本で買った食品や雑貨、医薬品などを中国へ送り込む動きが見らえた。しかし、それらは今、中国で「安く」買えるようになった。先日、中国から来た友人も「中国で安く買えるから」とほぼ手ぶらで帰っていった。
2021年にEMSの通関が電子化された。そのため、国によってはインボイスに英文表記が求められるようになった。ドイツなどは、品名の1つ1つについてHSコードを調べなければならないという手間が生じるようになったことから、私は家族への荷物が送りにくくなった。
一方で、中国の国際宅配・物流サービス企業が参入するようになった。国土交通省は2022年、順豊航空(FSエアラインズ、以下FS)に国際航空運送事業を許可した。同社は2011年から日本法人を東京に設立していたという。
当時、日本の運送事業者の一人は「既存の日本企業の中国向けのシェアにとっては打撃だ」と話していた。郵便局のEMS利用者は、中国資本が提供するサービスに流れた可能性もある。
ちなみに中国向けはHSコードの記入は必要ない。
中国で人気高まる日本の医薬品だが
最近、中国で日本の医薬品が人気だ。筆者のところにも上海の高齢者から湿布薬の「モーラステープ」を送ってもらえないか、という依頼があった。「モーラステープ」については、筆者自身が腰痛を患っていることから、幸い手元には未使用のものがある。
「これを送ってみてはどうか」と思った。また「そもそも医薬品は中国に送れるのか」と思い、FSの窓口に問い合わせてみた。その回答は次のようなものだった。
「個人宛の湿布でも、金額・量に制限があります。1回の宅配につき10パックまで、1人で使い切れる量に限ります。当社は1個1個申告するので、後から税金が発生するケースもあります」
はっきりしていて、大変わかりやすい回答だった。
一方で、同じことについてEMSを扱う日本郵政(0120-5931-55)に尋ねた。
「中国への医薬品の輸出については麻薬等は禁止ですが、医薬品全般がダメとはなっていません。ただ『税関の輸入制限の対象となるその他のもの』という記述があります。ここがはっきりしないので事前に中国の税関に問い合わせる必要があります」とのことだった。
中国の税関に問い合わせる?ここで私はEMS利用を断念せざるを得なかった。
そして念のため、近所の郵便局にも尋ねた。その回答は「処方箋薬でも中国に送れます、金額・量は問いません」ということだった。
求めに応じた医薬品提供は断念
同じ日本郵政の中でも見解は一致していないのはどういうことなのか。おまけにFSとも異なる回答だ。むしろ法律・法規を理解しているのはFSの方だ。もちろん中国資本の会社だから、そこは精通していて当然なのだが、私はむしろ日本郵政の“いい加減な情報提供”に呆れてしまった。
日本の制度や法律は国内的には「完備されたもの」でも、ひとたび海外が対象となると、「ゆるさ」「あいまいさ」が露呈してしまう。そして、こういう“いい加減さ”や“ゆるさ”は、脱法行為や犯罪に利用されてしまう。
今回、私は「モーラステープ」を中国の友人に送ることはやめた。考えてみれば、そもそもこれは処方箋薬(2026年度から保険適用外になる)であり、最終ユーザーは「私」である。もし、友人がこの薬を気に入り、「次も送ってくれ」となれば、私は永遠に中国への「横流し行為」を繰り返さなければならなくなる。
しかも、このようにして処方箋薬を「横流し」することは、私たちが保険料で支える日本の医療保険制度の維持にもかかわってくる。
日本の薬機法は「国民の健康を守るための法律」であり、輸出については「知らない」というスタンスである。つまり、日本から医薬品された医薬品が他国の人々の健康にどう影響しようが関知せず、というわけである。
最近は日本の医薬品を転売・輸出する業者も出てくるようになった。このようにして隣国の人々の求めに応じて輸出を続けた場合、この先日本国内の医薬品の需給はどうなるのかと、ふと心配になってしまった。