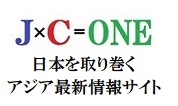今日は参議院選挙の投票日。カンカン照りの炎天下を、私は自転車をこいで都内のある団地に取材に向かった。1961年に建てられた都営住宅に住んでいるのは600世帯超。そのうち3割を外国籍の居住者が占めているという。
この団地では、外国籍の居住者の増加とともに、「ゴミ問題」と「騒音問題」が浮上した。自治会は「困ったなあ、どうしたもんかなあ」と手をこまねいていたが、一体誰がどこに住んでいるのかもわからないという状況だった。ところが、ある時期に会長が交代すると、解決に向けた第一歩が大きく動き出す。会長Yさんの粘り強さで居住者の名簿作りが進み、「どの国から何人」という団地の居住者の全体像が浮き彫りになったのだ。
同時並行して行ったのが、住民参加の「ゴミ出し説明会」だった。けれども肝心な外国籍居住者はほとんど参加しない。ここでも手をこまねいていると、ある人が「団地にはこういう人がいるよ」とネパール出身のSさんを紹介してくれた。Sさんの日本の生活は10年を超え、日本語もたいへん流暢だ。Y会長はSさんに自治会の悩み事を相談すると、即座に「参加者を集めましょう」ということになり、次に開催した「ゴミ出し説明会」には多くのネパール人居住者が集まった。
この成功には自治会とネパール居住者のブリッジ役を引き受けてくれたSさんのリーダーシップと、日本人ではとても思いつかないような発想が決め手となった。もちろん、Y会長とSさんの息があった両輪体制のおかげでもある。
この団地では2022年に防災訓練を行ったことがある。この活動を通して、高まったのは防災意識だけではなかった。日頃は各戸内にこもり「横のつながり」がない居住者たちが、互いの顔を認識することになった絶好の試みとなった。
Y会長が着手した「名簿作り」、Sさんが築いた「ネパール人動員のための知恵」以外にも、この団地にはさまざまな工夫が潜在する。筆者は、こうした大団地のノウハウも、規模の小さいマンションにも応用できるのではないかと考えている。このように“外国人問題”はマクロではなく、ミクロの視点で見ることが肝要だ。
一方で、その日に初めて会ったネパール人のSさんのこんな話が印象的だった。
「2014年は1万7000人だったが、現在は20万人。ネパール人は本当に多くなった。ただ、催し物などで会場をレンタルしても食べれば食べっぱなしで、掃除もしない。だからネガティブな視線で見られてしまう。ネパール人の課題は『自分が変わらないといけない』ということだ」
今後のSさんのリーダーシップに期待したい。(姫田小夏)