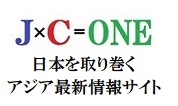2025年の参議院選挙では「外国人」に対する政策がキャスティングボードを握っている。SNSではフェイクとおぼしきものも含めて、外国人をキーワードにした動画が拡散されている。一歩間違えれば、「ヘイト」になりかねない社会現象でもあり、「このままでは社会が分断される」とする懸念も出ている。
21世紀において社会が多文化共生に向かうのはあるべき方向だが、揉めているのは“各論”だ。だから、「外国人」と十把一絡げにせず、“各論”において政策の方向性と必要な制度を再設計する必要がある。
在留資格で分類すれば、外国人労働者、留学生、経営・管理などの身分で日本に滞在する人々に対し、いかに国がルールを明確にし、それを順守させているのか、が問われることになる。
アジアビズのメンバーのひとりは「“カオスグローバル化”を進めてきたことが問題だ」と話していた。カオス化させたのは、政府もメディアも炎上を恐れて“外国人論”に蓋をしてきたからである。
日本の産業では、これまで「国籍問わず」で人や資本の参入を許してきた分野もあるが、金額・人数の多さで踏み込まれてしまえば到底持ちこたえることができない業界もある。もはや間尺が合わなくなっている実態に対して、国民保護の観点で制度設計をしなおさなければならないところに来ている。「日本人ファースト」のキーワードが出てきたのはこうした背景もあるだろう。この言葉の独り歩きは危険だが、国は国民の心情を察知しなければならないのではないか。
前出の当会メンバーは、日頃教育の現場に身を置くが「政府も学校もルールが曖昧だから、外国人留学生の受け入れを巡って現場はいつも翻弄させられている」と話していた。各論からは現場でのさまざまな問題点が明らかになる。今後は「現場目線」で問題を分析し、制度設計を見直すことが焦眉の課題だ。
先日、池袋の食品工場で働くネパール人と話したが、彼は「今の職場では、組織、事業、サービス、プロダクトにおいて何を大切にするかを教わった」とその職場環境を大変気に入っている様子だった。
こういうベストマッチングの事例を聞くと私もホッとするのだが、中には悪質な日本人経営者もいる。一方不法就労は、雇用主とのトラブルに遭い、ここから逃れ失踪者になったときに不法就労者になるケースが多い。
不法就労者問題は、技能実習や特定技能の制度を使って外国人労働者を扱う業界の経営者にも責任の一端がある。また、これから課題となるのは、日本の経営者における外国人労働者の権益保護の観点である。当会の別のメンバーは「うちはまず対企業への再教育から始めています」と話していた。
また、日本には経営・管理ビザで滞在している人々も多いが、その入り口の部分の条件がかなり低い。世界の先進国で生活する日本人は、「たかだか500万円の資本金で滞在を許すなんて、日本政府は外国人に対して非常に甘い」と批判している。現地でのビザ取得に相当苦労しているからこそ、こういう意見も出てくるようだ。
近年はマレーシアが外国人の滞在のハードルを引き上げた。日本人になじみがあるのは、同国での永住権の申請だが、それには「マレーシアの銀行口座に最低200万米ドル(2・9億円)以上の入金」が必要だという。中国でさえも日本人は簡単に就労ビザの取得ができなくなった。
どの国も外国人を含む労働者の確保は喫緊の課題だが、一方で国際社会全体を見れば「引き締めながら」「コントロールしながら」それを行っていることがわかる。
日本の“開放政策”は理解に苦しむ。このようなことだから、国民も疑心暗鬼になり、外国人との間に無用な摩擦を生むのである。(姫田小夏)