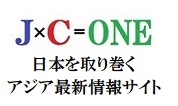6月26日の「アジアビズ・オンライン」では、当会を主宰する姫田小夏が外国人労働者の受け入れを巡って、日本と台湾の比較を行った。このコラムではそこから「台湾の在宅介護事情」を抜き出して、「台湾の在宅介護と笑いあり失敗ありのエピソード」をお伝えしよう。
まず、台湾の外国人総数は2024年で94万8066人で、外国人労働者(移工)は71万2158人、このうち介護職が19万6541人を占めている状況だ。
介護職が多いのは、台湾が在宅介護に依存する社会だからだ。「老人状況調査報告」(衛生福利部、2024年出版)によれば、65歳以上の老人は97.9%が在宅で生活しており、施設で生活している老人は2.1%に過ぎない。
その施設の中には、「おかゆしか食べさせてもらえないから、絶対に行きたくない」(高雄市在住の高齢者)と“劣悪な環境”のレッテルが貼られてしまうところもあるが、目下台湾では「長照2.0」という国家的長期介護戦略のもとで、家庭依存型の介護から制度依存型の介護へと転換が図られようとしている。
台湾の在宅介護に目を向ける日本企業
一方で台湾には今、“日本からの台湾詣で”が増えているという現象がある。台湾在住のコンサルタントによると「今後を見据えて、台湾の在宅介護を学びに来る日本のビジネスマンもいらっしゃいます」とのことで、台湾の住み込み型の在宅介護が日本でも注目され始めていることがうかがえる。
高齢者と寝食を共にし、食事や着替えの世話、マッサージから下の世話まで、すべてをひとりの外国人介護人材が行う「台湾モデル」。台湾の外国人介護人材は19万6541人で、男性はわずか1716人にとどまり、圧倒的に女性が多いのだが、台湾で在宅介護が実現できているのは、ひとえに彼女たちに「護身術」があるからだと言えるだろう。
高齢で足腰が立たなくなったといえどもあくまで男性は男性。隣のベッドで寝ている外国人介護人材に覆いかぶさってくることだってないとは言えない。台湾で外国人介護人材を雇用している陳さん(仮名)に尋ねると、「そもそもそういう元気があるなら介護はいらないわよね」と笑いつつ、次のように語ってくれた。
「確かに高齢になるとスケベになる傾向はある、久しぶりに若い子をみるんですから、おむつを替えたり足をマッサージしてくれるだけで元気になってしまうんです。実はうちのおじいちゃんも…」
“変な雇い主”でも対処できる東南アジア人材
結果として、手を出そうとしたおじいちゃんはフィリピン人の介護労働者に訴えられ、その後釜で来たベトナム人には逆に主導権を握られてしまったそうだ。このベトナム人には飲食店でおごらされ、スマホまでねだられる始末だったという。
陳さんは「フィリピンの女性は賢いし、高齢者に比べて力もあります。ベトナムの女性はさらにしたたかに振舞いますよ」とも加えた。
彼女たちは台湾に来る前に、労働者が主張できる権利をしっかり学んでいて、“変な雇い主”に遭遇したときの身の守り方を知っているのだ。外国人労働者の「権益保護」が浸透する台湾社会だからこその「住み込み型」とも言える。
さて、後釜のベトナム人介護労働者について言えば、おじいちゃんの遊び仲間のようになってしまい、家族には嫌われてしまったわけなのだが、当のベトナム人介護労働者をクビにしてしまったところ、「おじいちゃんは弱ってしまい車いすの生活になってしまった」(陳さん)という後日談もある。またこんなエピソードもある。
ある大金持ちの地主が独居に耐えられなくなり、周囲の勧めでベトナム人の介護人材(30代)を雇った。そのベトナム人は、介護職なのに服装はやけに露出度が高く、次第に妻のように振る舞うようになった。そしていつの間にか入籍…。
日本でなら一大事だ。だが、家族は慌てなかった。彼女を雇用する前にすでに財産は生前分与していたからである。「このベトナム人女性には一部現金が渡りますが、家族としては『それでおじいちゃんが元気なら』とむしろ歓迎しています」と事情通の陳さんは語っている。
日本にとってはハードルが高いが…
台湾ではダウン症の子を持つ家庭がフィリピン人の介護人材を雇っている例もある。「温厚で料理もうまい、子どもたちも英語を身に着けることができた、彼女の存在にどれだけ助けられているか」と明かす雇用主もいる。日本でも、外国人介護人材の住み込みが実現すれば、本人や家族にとってどれほどの助けになることか…。
日本にとって「台湾モデル」はハードルが高い。最初の壁となるのは「他人と同居?」の抵抗感と「場所がない」という狭い住宅構造だろう。
他方、過疎地に目を向ければ、大きな家に一人で住んでいる老人は多い。軽度ならばヘルパーさんが通いで面倒見てくれるだろうが、老化や認知症が進みいよいよ重度となったとき、施設なしでは生きてはいけない。
そのとき周辺に施設があるかどうかの未知数を思えば、今から「新たなモデルづくり」に挑戦する意味はある。防犯カメラの設置や定期的な見回りなどとるべき対策はいとまがないが、台湾の事例から学べることは「事前の対策で解決できることも多い」ということだ。
ちなみに陳さんも台湾でも外国人介護人材の家庭への派遣制度が始まるまでは、「住み込み介護なんかあり得ない」と思っていたそうである。
「台湾モデル」も試行錯誤の積み重ね結果であるとすれば、日本もまた「はじめの一歩」を踏み出す意味はあるのではないかと思う。(姫田小夏)