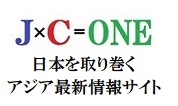外国人材が健やかに就労できる環境を
塚崎さんが働いているのは、設立して3年になる「登録支援機関」と呼ばれる企業だ。支援するのは特定技能制度で来日した外国人材。ゴミ出しや公共料金・税金の支払い、会社の就業規則の伝達など、慣れない日本で働く外国人材への支援は10項目にわたる。塚崎さんは「中国駐在15年、そもそも自分が異邦人でした。だからこそ外国人の気持ちに寄り添うことができるのではないかな、と思っています」と話す。
塚崎さんの会社が注目しているのはインドネシア人材だ。インドネシアの人口は2.8億人。2035年までに3.5億人になることが見込まれていて、いずれ米国を抜いて世界第3位の人口になるという点からも供給不安はない。しかも日本語を学ぶ人口は世界2位という親日国でもある。
インドネシア人は優しい人が多く、小さい頃から人助けの精神を教えられて育った人もいて、そのホスピタリティ溢れる働きぶりは、介護の現場にうってつけだと言われている。
「別の国の人材だと、手間を嫌がりおむつを履かせてしまうこともあるんですが、インドネシア人なら手を抜かずに根気強くおじいちゃんの下の世話までやってくれます。食品製造工場のラインで働くパートのおばさんの間でも『インドネシア人は、困ったことがあると、すぐに助けてくれる』と評判がいいんです」(塚崎さん)
ひと言で「アジア人」と言っても、現場での能力発揮は千差万別のようだ。国によっては「数回やると飽きる」「楽して怠ける癖が出る」などの性格が表れる場合もある。
来日費用の削減が課題
塚崎さんが日々心掛けているのは、インドネシア人材の来日費用の削減だ。来日費用の削減は、多額の借金をアジア人材に負わせ失踪者を出し、政策的な欠陥が指摘された技能実習制度が背景にあった。そのため、塚崎さんの会社が構築したのは、仲介業者を頼らずに「自己ルートで人材を探す」仕組みで、現在はSNSを活用して人材を集めているという。人材送り出しを担う現地の職業訓練校から紹介された人材を扱う場合もあるが、その会社と提携を結ぶに際して、現地で代表者と面談する他、各種資料の提出を求め審査し、「提出を嫌がる会社とは契約しません」と厳しく一線を引く。
また、日本語能力については、「日本語能力試験(JLPT、N1が最高水準)」の結果重視ではなく、「たとえJLPTでN4レベルであっても、話せる能力がN3レベルなら、その人材を採用しています」と話す。仲介業者任せにしないからこそ、ここで同社の「眼力」が光る。
塚崎さんの会社はわずか2年でノウハウを蓄積、増え続けるクライアントには「ドンピシャ」な人材を送り込む。「2名の募集が来たら2名を推薦します、ほぼ100%内定します」(同)と目下、好業績を上げている。
クライアント選びにおいても、多文化共生を意識できる会社なのかどうかを確認している。さらに塚崎さんは、インドネシアの習慣や価値観を、クライアントに伝えるブリッジとしても日々奔走する。頭部には触れない、人前で怒らないなど、インドネシア人が嫌がることもきちんと伝えている。
現場で生まれつつあるアジア人材のリーダー
空港のグランドハンドリングの業務にもインドネシア人材を送り込んでいる。仕事の内容は幅広く、スーツケースの上げ下ろしから、貨物の搭降載、航空機を駐機場で誘導するマーシャリングなど、いわゆる「空港の裏方」だが、車の運転免許が必要で、高い日本語能力とともに責任と緊張感を求められる現場だ。この現場ではすでに1期生が2期生を教えるという好循環が生まれていると言う。
特定技能制度では、日本人と同じ給与水準にすることが求められている。アジア人材であっても年齢とともに給与を上げている会社もあり、また会社に選ばれて外国人のリーダーになる人も少しずつ出てきていると言う。
「部門ごとに外国人としてのリーダーが出てくるなど、今まで日本企業にはなかったキャリアパスが出て来る可能性もあります。企業によっては、日本人を抜くような人材を育てようとしているところもあります」(同)
アジア人材はバックヤードからフロントラインへ――。塚崎さんの取り組みからは、日本で活躍するアジア人材の未来像が透けて見える。(2025年5月29日 アジアビズ・オンラインでの講演から)