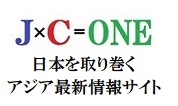2024年に来日して半年以上が経過、日本語学校で学ぶアジアからの留学生もだいぶ生活に馴染んできた様子だ。と同時に、日本語的には「これで大丈夫なのか」と、ちょっと気になる時期でもある。
日本語学習は一定のスピードで進んでいき、半年が過ぎるころには中級の教科書に突入する。学習は文語表現が多くなり、「~に限って」とか「~の上で」とか、難しい表現がどんどん出てくる。
その一方で、会話力となるととても中級レベルとは言い難い。たとえあいさつ程度の日常会話でもなかなかコミュニケーションがとりにくい。教科書の例文はスラスラ言えても、ひとたび教科書を離れると、その日本語は急にたどたどしくなってしまう。日本語で話しかけられても、すぐに日本語で反応でき、会話を続けられる学生は一握りだと言ってもいいだろう。
残念なのは発音だ。これだけ文法や語彙をガチガチと叩き込まれても、正しい発音ができなくて、会話がほとんど成立しないのだ。アクセントが違うと「火災」が「葛西」になってしまい、この留学生は「葛西の爆発」(25年5月の火災での爆発事件)について話したいのか、「火災と爆発」(最近多発する社会的ニュース)について話したいのか、理解するまでに時間がかかってしまう。
残念ながら、日本語学校の教育は相変わらず難しい「文法・語彙」「漢字」が中心であり、「実際にしゃべれるかどうか」の能力引き上げについては完全に後回しになっていると言わざるをえない。
一方で、彼らには日本人の友達がほとんどいないというのも気になる。
私は、1971年に私費留学で来日、その後、東京農大に入学したベトナム人で70代のSさんと懇意にしているが、Sさんの時代はどうだったと聞くと、「大学では日本人の友達もできた。先生がベトナム人留学生を孤立させないように気を遣ってくれた」と言う。
翻って今はどうだろう。今では都内にも外国人が多すぎて、留学生に向ける関心は、学生数が少なかった70年代ほど高くはない。しかも誰もがスマホを手にする「個」の時代である。日本人はみな自分のことで忙しく、相手が外国人であろうとなかろうと、他人に関心を向ける心の余裕はない。ましてや、留学生の日本語が聞き取りにくい発音なら、なおさら嫌がられてしまう。
そんな世知辛い都心で、留学生は何のために日本語を学び、どのようにして日本語を身につけていくのだろうか。
現代の日本語は、人と仕事は結んでも、人と人とを結ばない言葉になっていやしないかと、とても気になるのである。(日本語教師A)